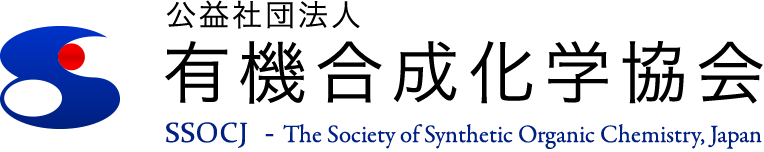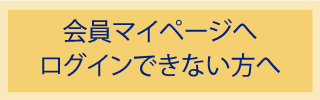イベント - 協会本部 –
2025年度 有機合成化学講習会 終了しました
- 日時
- 2025年12月12日(金)13:00~19:30 (情報交換・交流会 18:00~19:30)
- 場所
- 化学会館5階会議室
(東京都千代田区神田駿河台1-5)
[交通] JR中央・総武線「御茶ノ水駅」 御茶ノ水橋口から徒歩3分
- 主催
- 有機合成化学協会
共催:日本薬学会/協賛:日本化学会/後援:日本農芸化学会
テーマ 「企業における有機合成化学:理念・製品化・ブレークスルー」
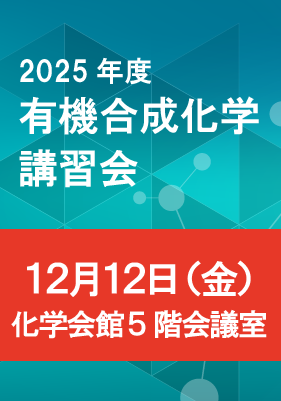 有機合成化学講習会は、有機合成の基礎から最新の知見までを“講義”というスタイルで提供するユニークなイベントとして長く親しまれてきました。特に企業会員にとっては、最新情報を深く学べる機会として重宝されてきました。
有機合成化学講習会は、有機合成の基礎から最新の知見までを“講義”というスタイルで提供するユニークなイベントとして長く親しまれてきました。特に企業会員にとっては、最新情報を深く学べる機会として重宝されてきました。
コロナ禍を経てここ数年は分野を絞り、より深く情報提供を行うスタイルを取ってきましたが、昨年度から有機合成化学を深く学ぶというところは大切にしつつ、視点を少し変えて、「有機合成化学がいかにして製品化や高収益化に結びついているのか?」、「企業はどのような理念で研究に挑み、困難を克服しているのか?」ということについて産業界側から情報提供を行い、企業間そしてアカデミアとの深いコミュニケーションを実現したいと考えています。そのため、本講習会が若手から中堅の企業会員にとって、現在の研究に直結する貴重なヒントや、困難に立ち向かう勇気、そして成功への心構えが得られるきっかけとなることを期待しています。また、学生会員にとっても本講習会が企業研究における有機化学の果たす役割の理解向上につながる機会にできると考えています。
講演につきましては「材料開発」、「触媒開発」、「バイオ関連」、「プロセス化学」の各分野からお願いしました。講演会後には交流会も企画しておりますので、より深いコミュニケーションからネットワークを広げる場としてご活用いただけると考えています。多数の参加申し込みを心よりお待ちしております。
プログラム
〔各講義とも質疑応答含め60分〕
13:00~13:05 開会挨拶 本会事業委員長 松本 隆司(東京薬大薬)
13:05~14:05 講演(1) [座長: 柴田 雅史(事業委員、三菱ケミカル(株))]
平居 丈嗣 (AGC株式会社 材料融合研究所 有機材料部 主幹研究員)
「燃料電池の実用化を支えるフッ素系電解質ポリマー開発」
- フッ素系電解質ポリマーは、食塩電解など現代の化学産業を支えるキーマテリアルとして重要な役割を担ってきました。本講演では、この材料の燃料電池への応用に関する我々の取り組みを紹介します。実用化における課題であったポリマーの耐久性向上に対し、独自の「ラジカルクエンチャー技術」がどのように貢献したか、また、電池性能の向上に寄与する「高酸素透過性アイオノマー」をいかに開発してきたか、これら合成化学を基盤とする材料開発が、燃料電池の実用化と進化を支える技術内容について取り上げたいと思います。
14:10~15:10 講演(2) [座長: 平田 泰啓(事業委員、AGC(株))]
清水 史彦 (三菱ケミカル株式会社 グローバルリサーチパートナーシップ部 部長)
「エチレン/アクリル酸エステル共重合のための均一系錯体触媒の開発」
- α-オレフィンと極性ビニルモノマーの共重合は、ポリオレフィンにおける長年の課題です。一方、エチレンとアクリル酸エステルの共重合は、既存の高圧ラジカル重合プロセスで、既に商業化されています。しかしながら、ここで得られる共重合体は、分岐が高度に発達しているため、耐熱性・強度が低いという課題があります。そこで私たちは、エチレンとアクリル酸エステルの共重合によって、直鎖状の共重合体生成を可能にする均一系錯体触媒の開発に取り組みました。具体的には、工業的に有利なNiを中心金属とする錯体触媒に着目し、リガンドに「メトキシ効果」を導入した新規触媒を設計しました。この触媒によって、直鎖状の高分子量共重合体を、高活性かつ工業的に好ましい重合温度で得ることに成功しました。また、DFT計算で重合機構を明らかにしました。
(休憩)
15:25~16:25 講演(3) [座長: 奧山 圭一郎(事業委員、アステラス製薬(株))]
藤井 友博 (味の素株式会社 バイオ・ファイン研究所 主任研究員)
「化学的抗体位置特異的修飾法AJICAP®の開発」
- 抗体薬物複合体(ADC)などの抗体複合体は上市品数や臨床試験が増加している。従来は抗体中のCysやLys残基にランダムに薬剤を結合させる方法が主流だが、構造の不均一性が治療濃度域の達成を妨げている。そこで抗体Fc部位に親和性を持つペプチドを使った位置特異的修飾法AJICAP®コンジュゲーションを開発した。本手法は有機合成化学的修飾法で、高収率、高品質にてADCを調製できる。さらに、安定性と親水性に優れたAJICAP®リンカーも開発し、薬効と安全性を向上させた。本講演ではAJICAP®技術の詳細と応用例を紹介する。
16:30~17:30 講演(4) [座長: 小宮山 真人(事業委員、中外製薬(株))]
釣谷 孝之 (塩野義製薬株式会社 製薬研究所 所長)
「SHIONOGIにおける原薬開発プロセスの紹介」
- 製薬企業において有機合成化学を活用する研究には大きく「創薬化学研究」と「プロセス化学研究」の2つがある。創薬化学研究は医薬品となる有望な化合物を創り出す研究であり、有機化学を駆使してモノを創ることを目的とする。一方で、プロセス化学研究は創薬化学研究にて創り出された医薬品候補化合物を安定的に社会に供給可能な工業的プロセスを造りあげる研究であり、有機化学でモノを造ることを目的とする。本講演では、弊社にてプロセス開発を進めているS-892216原薬を題材に取り上げ、SELECT (Safety, Environmental, Legal, Economics, Control, Throughput) の視点からプロセス化学研究の概要を説明する。
(移動と準備)
18:00~19:25 情報交換・交流会
情報交換・交流会 (立食形式を予定)
19:25~19:30 閉会のことば
本会事業委員会副委員長 釣谷 孝之(塩野義製薬)
申込方法
以下の専用フォームよりお申込みください。
申込定員:60名(先着順)
申込締切:11月28日(金)
受講料(税込み)
| 区分 | 一般(個人会員・法人会員) | 学生 [*3] | |
|---|---|---|---|
| 企業所属 | アカデミア職員、研究生など | ||
| 主催・共催等会員 [*1] | 18,000円 | 14,000円 | 8,000円 |
| 会員外 | 28,000円 | 21,000円 | 15,000円 |
| 本会シニア会員 [*2] | 10,000円(66歳以上の有機合成化学協会・個人会員) | — | |
※受講料には、情報交換・交流会への参加費を含む。
*1) 本会の法人会員企業等に所属する方はこの区分でお申込みください(個人では本会非会員の方も含む)。
共催等会員には、共催、協賛、後援の各学会の個人会員が該当します。
*2) 本会シニア会員=66歳以上の有機合成化学協会個人会員。
*3) 学生は、学部や大学院専攻科に学部生、院生として在籍している方とします(研究員等は含みません)。
申込先・問合せ先
- 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1-5
- 公益社団法人有機合成化学協会
- TEL.03-3292-7621
- e-mail:ssocj-eventssocj.or.jp