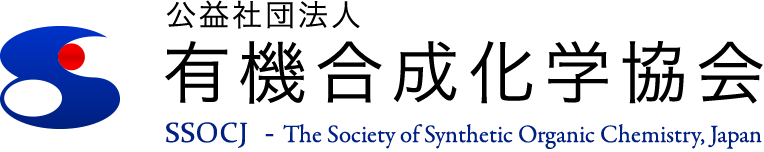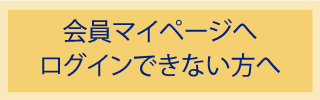イベント - 協会本部 –
平成29年度 後期(秋季)有機合成化学講習会 開催報告 終了しました
- 日時
- 平成29年11月15日(水)~16日(木)
1日目 9:40~18:30(イブニングセッション&ミキサー:自由参加)
2日目 9:30~17:00
- 場所
- (公社)日本薬学会長井記念館長井記念ホール
東京都渋谷区渋谷2-12-15 / TEL.03-3406-3326(地図)
- 主催
- 有機合成化学協会(共催:日本化学会、日本薬学会、日本農芸化学会)

開催報告
有機合成化学講習会は通常の学会やシンポジウムとは一線を画し、アカデミアの最先端でご活躍の先生は勿論のこと、産業界からも一流の講師をお招きし、最新の研究成果だけでなく、研究の背景や着想に至った経緯、研究を進める上での苦労話や失敗談、実際にその技術を使いこなす上でのコツなどを丁寧に解説いただける貴重な機会として、非常に特徴のあるものです。受講者の中心は企業の若手研究者で、事前にテキストを受け取り予習していただき、指定席でじっくりと学べる環境・スタイルをとっています。さらに内容習得をより深めるために、ご講師と参加者が直に質疑応答・討論も可能なミキサー&イブニングセッションを初日の講習終了後に設け、様々な企業からの参加者同士の情報交換や人脈形成の場としても非常に有意義な会として好評をいただいており、本講習会ならでは大きな魅力のひとつでもあります。
今回の講習会は、「未来指向型もの創りのアプローチ」と題して、活用が期待される新反応や新触媒の開発、新分子の材料や医薬品の創製、天然物の香料への応用、また有機物の微粒子化、反応経路の自動検索プログラム、さらには細胞治療、再生医療への利用など、多岐に渡る領域でご活躍されておられる12名の先生方を産学からお招きしました。「ものづくり」の根幹をなす有機合成化学は、日本の強みとして、基礎研究から実用化研究に至るまで活発な研究がなされ、産業の発展に寄与してきました。この二日間は、有機合成化学を活用した次の将来を描く、数多くの有益な合成反応や新分子の発見だけでなく、新分子のこれまでにない活用法にも触れる、貴重な機会となりました。
第1日目
 上杉志成先生(京大化研)による「細胞を操る合成化合物」で講習会がスタート致しました。演題の通り、細胞生物学のツールとして合成有機化合物を用いることにより、生命現象の操作・解析を新たな切り口で行っておられ、未発表の結果までご紹介いただきました。“新感覚”化合物ライブラリーという概念や、見出された化合物の細胞治療への活用法など、合成有機化合物の新しい使い方や未来が垣間見える、大変面白い講義でした。
上杉志成先生(京大化研)による「細胞を操る合成化合物」で講習会がスタート致しました。演題の通り、細胞生物学のツールとして合成有機化合物を用いることにより、生命現象の操作・解析を新たな切り口で行っておられ、未発表の結果までご紹介いただきました。“新感覚”化合物ライブラリーという概念や、見出された化合物の細胞治療への活用法など、合成有機化合物の新しい使い方や未来が垣間見える、大変面白い講義でした。
 続いて、上條真先生(山口大院)より「飽和炭素鎖を官能基化する光反応の開発」の演題でご講義いただきました。光励起によって生成する高反応性ラジカル種を用いて低反応性のC(sp3)-H結合を直接的に官能基化するという、先生の一連の研究成果だけでなく、光反応の基礎からご教示いただき、大変勉強になる講義でした。フロアからの質疑応答も非常に活発であり、本分野に関する期待値の大きさが覗えました。
続いて、上條真先生(山口大院)より「飽和炭素鎖を官能基化する光反応の開発」の演題でご講義いただきました。光励起によって生成する高反応性ラジカル種を用いて低反応性のC(sp3)-H結合を直接的に官能基化するという、先生の一連の研究成果だけでなく、光反応の基礎からご教示いただき、大変勉強になる講義でした。フロアからの質疑応答も非常に活発であり、本分野に関する期待値の大きさが覗えました。
 午後前半のセッションは産業界より講師をお招きし、渡辺広幸先生(長谷川香料(株))による「食品中に存在する微量天然物の香料への応用」から始まりました。天然から得られる香油中に含まれ、極微量ながらも必須である成分の解析・同定に関する手法や、我々が普段口にする加工食品の安全と付加価値向上をサポートしていただいていることや、コスト面や製造管理面で他の製造業と異なる部分のお話などもあり、実に興味深い講義でした。
午後前半のセッションは産業界より講師をお招きし、渡辺広幸先生(長谷川香料(株))による「食品中に存在する微量天然物の香料への応用」から始まりました。天然から得られる香油中に含まれ、極微量ながらも必須である成分の解析・同定に関する手法や、我々が普段口にする加工食品の安全と付加価値向上をサポートしていただいていることや、コスト面や製造管理面で他の製造業と異なる部分のお話などもあり、実に興味深い講義でした。
 前川敏彦先生(富士フイルム)より「リコンビナントペプチド技術の再生医療への活用」の演題でお話いただきました。写真フィルム開発で培ってきたコラーゲン技術を活用すべく、再生医療3大要素の一つである細胞接着足場材料への展開に関してご説明いただきました。自社強み技術を他分野へ展開する着想と戦略、再生医療への実応用例も含め、受講者の中心である企業R&D担当の方々にとっては、大変に興味深いお話であったと思われます。
前川敏彦先生(富士フイルム)より「リコンビナントペプチド技術の再生医療への活用」の演題でお話いただきました。写真フィルム開発で培ってきたコラーゲン技術を活用すべく、再生医療3大要素の一つである細胞接着足場材料への展開に関してご説明いただきました。自社強み技術を他分野へ展開する着想と戦略、再生医療への実応用例も含め、受講者の中心である企業R&D担当の方々にとっては、大変に興味深いお話であったと思われます。
 コーヒーブレイクを挟み、「チオ尿素型有機分子触媒の化学」の演題で竹本佳司先生(京大院薬)よりご講義いただきました。尿素型有機分子触媒に関して、先生ご自身の研究成果だけでなく、他研究グループの報告例に関してなど、歴史的な変遷に関しても詳細にご説明していただきました。水素結合相互作用を巧みに活用・駆動力とする、大変複雑な反応系であるため、その触媒反応機構の詳細解明や、独創的な触媒設計には感嘆いたしました。
コーヒーブレイクを挟み、「チオ尿素型有機分子触媒の化学」の演題で竹本佳司先生(京大院薬)よりご講義いただきました。尿素型有機分子触媒に関して、先生ご自身の研究成果だけでなく、他研究グループの報告例に関してなど、歴史的な変遷に関しても詳細にご説明していただきました。水素結合相互作用を巧みに活用・駆動力とする、大変複雑な反応系であるため、その触媒反応機構の詳細解明や、独創的な触媒設計には感嘆いたしました。
 初日の最終講義は、伊丹健一郎先生(名大ITbM)による「触媒が拓く分子ナノカーボン科学」でした。一般にも広く知られることとなったカーボンナノベルト合成を含め、歴史的には古くから考察されながらも合成例の無い高難度分子の創生を、独自の新戦略・新反応・新触媒の開発によって切り拓いてきた詳細を、未発表の結果ならびに研究に対する指針・信条なども交えてお話しいただきました。初日最後を飾るに相応しい、まさに薫陶を受ける講義でした。
初日の最終講義は、伊丹健一郎先生(名大ITbM)による「触媒が拓く分子ナノカーボン科学」でした。一般にも広く知られることとなったカーボンナノベルト合成を含め、歴史的には古くから考察されながらも合成例の無い高難度分子の創生を、独自の新戦略・新反応・新触媒の開発によって切り拓いてきた詳細を、未発表の結果ならびに研究に対する指針・信条なども交えてお話しいただきました。初日最後を飾るに相応しい、まさに薫陶を受ける講義でした。
ミキサー&イブニングセッション
 1日目の講習会終了後、会場隣のロビーにてミキサー&イブニングセッションが行われました。2日目にご登壇される先生方も含めて講師の先生方にご参加いただき、多数の受講者も参加されておりました。軽くお酒を入れながらの和気藹々とした雰囲気で、先生方との講演内容に関するディスカッション、参加者同士の情報交換や人脈形成の時間として大いに盛り上がりました。
1日目の講習会終了後、会場隣のロビーにてミキサー&イブニングセッションが行われました。2日目にご登壇される先生方も含めて講師の先生方にご参加いただき、多数の受講者も参加されておりました。軽くお酒を入れながらの和気藹々とした雰囲気で、先生方との講演内容に関するディスカッション、参加者同士の情報交換や人脈形成の時間として大いに盛り上がりました。
第2日目
 前田理先生(北大院理)による「有機合成反応の系統的な機構解析と経路予測にむけて:反応経路自動探索プログラムGRRMを用いたアプローチ」で二日目の講習会がスタート致しました。先生は人工の力を反応系に加えて仮の反応経路を算出し、再度実の経路を算出する逆転のアプローチで、計算負荷を圧倒的に少なくすることに成功されました。反応機構解析以外にも、機能性分子設計においても強力なツールになることが期待されており、これからの進歩が注目されます。なお2017年度版のGRRMプログラムが近日中にリリースされるそうです。
前田理先生(北大院理)による「有機合成反応の系統的な機構解析と経路予測にむけて:反応経路自動探索プログラムGRRMを用いたアプローチ」で二日目の講習会がスタート致しました。先生は人工の力を反応系に加えて仮の反応経路を算出し、再度実の経路を算出する逆転のアプローチで、計算負荷を圧倒的に少なくすることに成功されました。反応機構解析以外にも、機能性分子設計においても強力なツールになることが期待されており、これからの進歩が注目されます。なお2017年度版のGRRMプログラムが近日中にリリースされるそうです。
 続いて、産業界より阿部博行先生(日本たばこ産業株式会社)から「MEK阻害薬Trametinib(Mekinist®)の創薬研究とケミカルバイオロジー」の演題でご講演いただきました。本化合物は皮膚がんであるメラノーマを適用として米国(2013年)、欧州(2014年)、国内(2016年)と承認された、MEK阻害薬としてfirst-in-classの分子標的薬です。化合物の開発経緯は有機合成化学者として非常にエキサイティングで、商業的なインパクトも併せて、フロアからの質疑応答も非常に活発でした。
続いて、産業界より阿部博行先生(日本たばこ産業株式会社)から「MEK阻害薬Trametinib(Mekinist®)の創薬研究とケミカルバイオロジー」の演題でご講演いただきました。本化合物は皮膚がんであるメラノーマを適用として米国(2013年)、欧州(2014年)、国内(2016年)と承認された、MEK阻害薬としてfirst-in-classの分子標的薬です。化合物の開発経緯は有機合成化学者として非常にエキサイティングで、商業的なインパクトも併せて、フロアからの質疑応答も非常に活発でした。
 午後前半のセッションは、平沢泉先生(早大先進理工)による「晶析法によるナノサイズ領域の粒子生成」から始まりました。近年重要性を増している有機ナノサイズ粒子の作製法に「高速核化&核化・成長・凝集抑制」の晶析工学的な戦略でのアプローチについてご紹介頂きました。企業の製造プロセスにおいてはろ過性改善のために晶析サイズを大きくすることが要求されますが、本アプローチは全く逆の方法を用いており、興味深いご講演でした。
午後前半のセッションは、平沢泉先生(早大先進理工)による「晶析法によるナノサイズ領域の粒子生成」から始まりました。近年重要性を増している有機ナノサイズ粒子の作製法に「高速核化&核化・成長・凝集抑制」の晶析工学的な戦略でのアプローチについてご紹介頂きました。企業の製造プロセスにおいてはろ過性改善のために晶析サイズを大きくすることが要求されますが、本アプローチは全く逆の方法を用いており、興味深いご講演でした。
 更に、山子茂先生(京大化研)より「ラジカル重合を用いた線状および分岐高分子の制御合成」の演題で、有機テルルを用いたリビングラジカル重合の原理と最近の進歩に関してご講演いただきました。現在では複数の商品に実用化されているようで、産業上極めて有用な反応にまで成長しています。発見の端緒になったアイデアは極めてシンプルですが、普遍性に富んでおり、その急速な発展・展開には理由があるのだなあと、考えさせられる講義でした。
更に、山子茂先生(京大化研)より「ラジカル重合を用いた線状および分岐高分子の制御合成」の演題で、有機テルルを用いたリビングラジカル重合の原理と最近の進歩に関してご講演いただきました。現在では複数の商品に実用化されているようで、産業上極めて有用な反応にまで成長しています。発見の端緒になったアイデアは極めてシンプルですが、普遍性に富んでおり、その急速な発展・展開には理由があるのだなあと、考えさせられる講義でした。
 コーヒーブレイクを挟み、「有機合成化学を基盤とした核酸医薬品の高機能化研究」の演題で釘宮啓先生(塩野義製薬(株))よりご講義いただきました。近年注目を集める核酸医薬品に関して、塩野義製薬での貴重な研究成果を詳細にご説明していただきました。低分子医薬開発で培った化学合成力や評価アセットを活用することで、新しい創薬プラットフォーム構築を検討しており、創薬系R&D担当の方々にとっては、大変に興味深いお話であったと思われます。
コーヒーブレイクを挟み、「有機合成化学を基盤とした核酸医薬品の高機能化研究」の演題で釘宮啓先生(塩野義製薬(株))よりご講義いただきました。近年注目を集める核酸医薬品に関して、塩野義製薬での貴重な研究成果を詳細にご説明していただきました。低分子医薬開発で培った化学合成力や評価アセットを活用することで、新しい創薬プラットフォーム構築を検討しており、創薬系R&D担当の方々にとっては、大変に興味深いお話であったと思われます。
 二日目の最終講義は、南川典昭先生(徳島大学医歯薬学研究部)による「分子内にリン酸基を有する化合物を医薬品にするために―プロドラッグの概念と有機化学―」でした。
二日目の最終講義は、南川典昭先生(徳島大学医歯薬学研究部)による「分子内にリン酸基を有する化合物を医薬品にするために―プロドラッグの概念と有機化学―」でした。
プロドラッグとは、体内あるいは目標部位に到達してから薬理活性をもつ化合物に変換され、薬理効果を発揮(活性化)するように化学的に修飾された薬のことで、講演では大型薬のプロドラッグ体の実例とともに、種々のリン酸プロドラッグ体の特徴についてご説明頂きました。
いずれのご講演も講習会ということで、専門外の参加者でも分かりやすく理解することができるようにご配慮いただきました。また、発見物語等の開発エピソードを盛り込んでいただき、興味深く拝聴することができました。各講師の方々には、大変感謝したく思います。
2017年度事業委員会委員
三井化学:田中 陽一、富士フイルム:髙橋 慶太