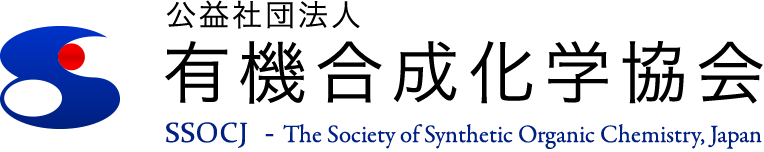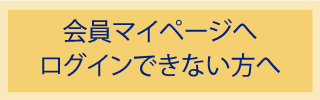イベント - 協会本部 –
2019年度 前期(春季)有機合成化学講習会プログラム 終了しました
- 日時
- 日時:2019年6月18日(火)~19日(水)
会場:日本薬学会長井記念館長井記念ホール
- 主催
- 主催 有機合成化学協会
共催 日本化学会、日本薬学会、日本農芸化学会
テーマ「新時代に飛躍する有機合成化学―機能性分子、材料から創薬まで―」
第1日目【6月18日(火)】
※下記時間は質疑応答を含まない/敬称略
1.「高機能分子の自動探索:自動設計と自動合成の融合による機能性分子発明の自動化へ」(13:10~14:00)
(産業技術総合研究所生命工学領域バイオメディカル研究部門主任研究員)石原 司
有機合成の極みの一つである医薬品の創出は、数年に渡る歳月と幾多の試行錯誤を伴い、生産力向上は製薬産業における至上命題と言える。近年における人工知能の進化は医薬候補化合物の設計を、ロボット技術の深化は化合物合成を、自動化しえる。我々は、医薬品創出に資する支援技術の確立に向け、自動設計と自動合成の具現化と融合による医薬候補化合物自動探索装置の完成を目指している。本講習では、創薬化学の現状を振り返りつつ、医薬候補化合物自動探索装置、ならびに、その試験稼働にて創製した化合物の概要を紹介する。
2.「睡眠障害治療薬を志向したオレキシン1/2受容体新規デュアルアンタゴニストLemborexant (E2006) の創製」(14:15~14:55)
(エーザイ㈱ニューロロジービジネスグループ(NBG)メディスンクリエーションディスカバリーニューロロジー筑波研究部長)寺内 太朗
オレキシンは、睡眠・覚醒状態を制御するキーメディエーターとしての生理的役割が示唆されており、不眠障害などに対する新たな創薬ターゲットとして注目されている。我々が創製したlemborexantは、ユニークな3置換シクロプロパン骨格を有するオレキシン1/2レセプターデュアルアンタゴニストであり、不眠障害を対象とした米国NDA申請を2018年に達成した。また、アルツハイマー型認知症に伴う不規則睡眠覚醒リズム障害を対象とした臨床開発も進行中である。本講習では、lemborexant創製につながった創薬研究の過程について発表する。
**ブレイク20分**
3,「知ってる人は知っている多糖誘導体系キラルカラムの意外な能力~アキラル異性体分離例と計算科学による認識機構の解明~」(15:30~16:10)
(㈱ダイセル新井工場CPIカンパニーライフサイエンス開発センター所長)大西 敦
多糖誘導体をキラル認識剤とするキラルカラムが、鏡像異性体だけでなく、広く位置異性体等の異性体類(アキラル化合物)の分子認識に優れていることは経験上、よく知られている。本講習では計算化学とアキラル化合物のクロマト保持挙動から、多糖系ポリマーによるアキラル化合物分離、キラルも含めた分子形状認識の考察とその応用例について報告する。
4.「セルロースナノファイバー開発の取り組み状況」(16:25~17:05)
(日本製紙㈱研究開発本部CNF研究所長)河崎 雅行
日本製紙では木質バイオマスを利用した新規事業の開発を推進しており、その中でもセルロースナノファイバー(CNF)の開発に注力している。CNFは高い結晶性を有した天然ナノ素材で、自動車の軽量化を目指した各種部材、塗料・化粧品・食品などの添加剤、フィルム・不織布と複合化した高機能シートなど多様な利用が考えられている。日本製紙では各種CNFを製造しているが、その中で木質パルプを化学変性してナノ分散したTEMPO酸化CNF、カルボキシメチル化CNFについてその製法、特徴および用途開発の取り組み状況を紹介する。
5.「核酸標的低分子創薬を支えるゲノム化学」(17:20~18:10)
(大阪大学産業科学研究所教授)中谷 和彦
ヒトゲノムの約8割はRNAに転写され、その多くが非翻訳RNAとして機能している。mRNAやこの非翻訳RNAを含めたDNA・RNA(以下核酸)は、従来創薬標的とされていた蛋白質とともに、今後重要な創薬標的となると考えられている。核酸を標的とする核酸創薬が盛んに研究されていますが、新たな創薬モダリティーとして「核酸標的低分子創薬」が、製薬企業各社の開発計画に上がりつつある。本講習では、核酸を化学的な視点で研究するゲノム化学から最新の低分子と核酸の相互作用研究について紹介する。
★★イブニングセッション(於;ロビー)★★(18:25~19:55)
第2日目【6月19日(水)】
6.「有機ラジカルを用いるタンパク質修飾法の開発と応用」(09:45~10:35)
(東京大学大学院薬学系研究科講師)生長 幸之助
タンパク質化学修飾法は、幅広い生命志向型応用に魅力があるツールである。我々は以前、有機ラジカル試薬を用いる金属フリーなトリプトファン選択的タンパク質修飾法を開発した。トリプトファンはほとんどのタンパク質に含まれる一方、他の天然アミノ酸に比べ表面露出数が少ない。このため本反応は均質な修飾体を得やすいという特長がある。講習会では、本反応の医薬応用および交差反応性を抑えるための取り組みについて述べる。
7.「柱型環状ホスト分子ピラー[n]アレーンの創成と空間材料化学への展開」(10:50~11:40)
(京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻教授)生越 友樹
リング状ホスト分子は、その空孔内部にゲスト分子を取り込むというホスト-ゲスト機能を示すため、有機化学・超分子化学の分野において重要な鍵化合物である。2008年に我々は、簡単に合成することができる正n角柱状のリング状ホスト分子「ピラー[n]アレーン」を見出した。日本発のリング状ホスト分子「ピラー[n]アレーン」は、今では世界中の化学者に利用されるようになっている。本講習では、ピラー[n]アレーンの特徴、及び最新のピラー[n]アレーンの応用展開について紹介する。
☆昼食&ランチョンセミナー&展示
8.「有機合成で新しいケミカルバイオロジーツールを創る」(13:30~14:20)
(九州大学大学院薬学研究院教授)平井 剛
ケミカルバイオロジー研究に利用可能な分子ツールは、蛍光プローブや天然物・生物活性物質の誘導体など、これまでにたくさん開発されてきた。しかし、生命現象の解明にはまだ十分とは言えない。演者らは、独自の分子設計概念の下、新しいツール分子の開発に取り組んでいる。本講習では、糖(脂質)-タンパク質相互作用の解明に寄与することを目的とした研究について、最近までの成果を紹介する。
**ブレイク20分**
9. 「稠密に官能基化された天然有機化合物の合成研究:複雑な分子を読み解く」(14:55~15:45)
(東京工業大学理学院准教授)大森 建
複雑で一見手のつけようもなく見える天然有機化合物も、そこに潜んでいる基本的な有機合成的要素を探り出しそれを理解すると、これまで困難と思っていた合成が、まるで解けた知恵の輪のように、いとも簡単に実現できることがある。本講習ではいくつか実例を挙げ、個々の場面でどのように問題を把握し、考え、それを解決したかを解説する。
10.「核酸医薬開発に向けた機能性人工ヌクレオシドの創製」(16:00~16:50)
(大阪大学大学院薬学研究科教授)小比賀 聡
近年、新たな創薬モダリティとして核酸医薬が注目されている。我々は核酸の化学構造の中でも特に糖部(フラノース環部)に着目し、そのコンホメーション変化を抑制することで、相補鎖との二重鎖が安定化されるとの考えのもと、架橋型人工核酸2’,4’-BNA/LNAを世界に先駆け設計・合成した。それ以降、我々は核酸医薬への利用を念頭に、新たな架橋型人工核酸の開発を継続して行なっている。本講習では、いくつかの架橋型人工核酸についてその設計コンセプトから合成や機能の一端を紹介したい。
閉会挨拶 17:05